2024.06.26
電話対応マニュアルの作り方|テンプレート・練習で使える例文

電話対応を円滑に行うためには、電話対応マニュアルがあるといいでしょう。
電話対応の経験に左右されず、一定の品質を担保できます。
とはいえゼロから作るのは難しい上に、マニュアルだけでは解決しない問題があるのも事実です。
本記事では 電話対応マニュアルの重要性や作り方、電話対応する際の担当者が注意する点などを解説します 。
効果的な電話マニュアルを作成して、品質担保に努めましょう。
■合わせてよく読まれている資料
「営業効率をアップさせるトークスクリプト作成法」も合わせてダウンロードいただけます。

目次
ビジネスにおける電話対応の重要性

ビジネスにおける電話対応は、顧客と接点を持つ大切な場でもあります。
実際は声だけのやりとりですが、電話対応は会社の「顔」と言っても過言ではないほど、相手に与える印象が変わる大事なもの。
受け答えの内容を一定の水準に保つためにはマニュアル作成が不可欠です。
しかし、それと同時に電話対応する人物の声で印象が変化する点にも、注意しなければなりません。
暗かったり早口であったりすると、相手はいい印象を持ちません。
電話対応の3原則 は、次の3つです。- 明るく
- はっきり
- 聞き取りやすいペース
3原則を意識して対応することで、印象よく評価してもらえることが多いです。
電話対応の研修においては、電話の内容よりも話し方や声のトーンに注力する企業も見受けられます。
電話対応マニュアルの作り方
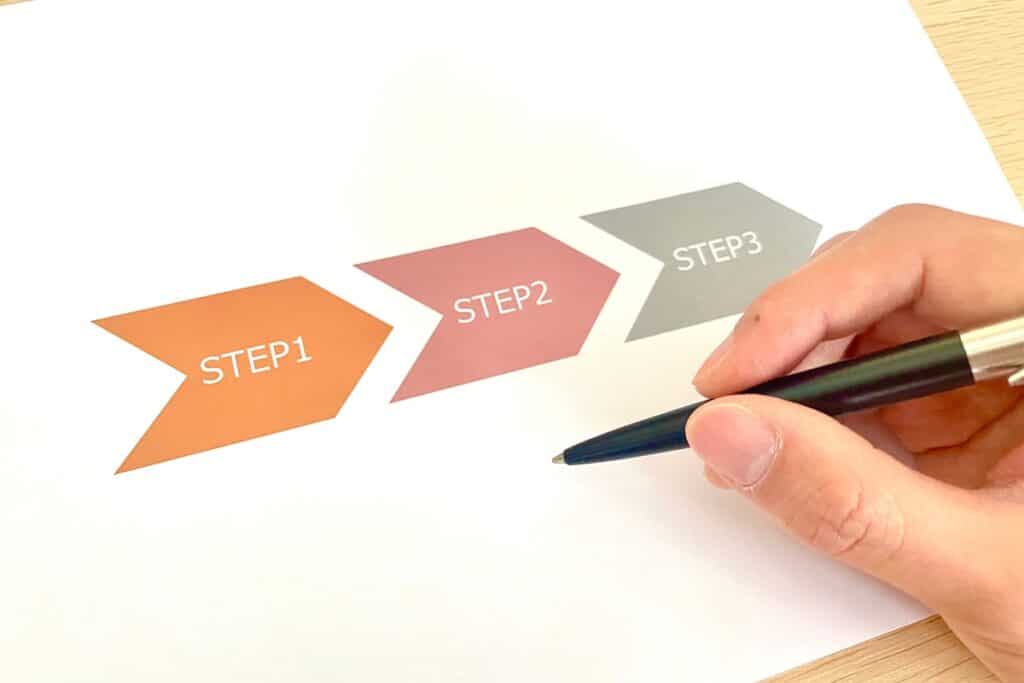
電話対応マニュアルの作り方は、以下の手順に沿って実施しましょう。
完璧ではないにしても、電話対応マニュアルの大枠ができあがります。
- 基本ルールの設定
- トークスクリプトの作成
- イレギュラーが発生した際の対応方法
上記の内容に関して、順に解説します。
基本ルールの設定
まずは基本ルールの設定です。
社内での電話対応の 基本的なルールを決めて、マニュアルに盛り込みましょう 。
例えば3コール以内で受話器を取る、名乗り方を統一するなどです。
また受けるときだけではなく、電話をかけるときの基本ルールの統一も併せて行いましょう。
トークスクリプトを作成する
トークスクリプトとは、電話をかける・受ける際にどのような流れでトークを展開するかを、図式化したものです 。さまざまなテンプレートがあり、各社独自にアレンジをしており、もっとも一般的な形式はフローチャートです。
相手の反応によって変わる答えを探しやすく、新人教育から品質の平準化まで幅広く利用できます。
アウトバウンド向けのトークスクリプトの作り方は、「トークスクリプトの作り方|営業ですぐに使える例文も紹介!」で詳しく解説しています。
イレギュラーが発生した際の対応方法
FAQの作成やクレームなど、イレギュラーが起こった際にどのように対応すればいいのかは、マニュアルに入れておくべきです。
保留のルールや、上席者へのエスカレーション方法などがこれに該当します。
特にクレームは、間違った対応や不誠実だとみなされる対応をすると、大問題へと発展することも少なくありません。
担当者が不在であっても、 誰が電話に出ても適切な対応ができるようにマニュアル化しましょう 。
■合わせてよく読まれている資料
「営業効率をアップさせるトークスクリプト作成法」も合わせてダウンロードいただけます。

【シーン別】電話対応のポイントとテンプレート

シーン別の電話対応のポイントについて解説します。
マニュアルに盛り込んだ方がいいテンプレートについても解説しているので、ぜひ参考にして電話対応マニュアルを作成しましょう。
電話対応の基本的なマナー
電話対応の基本的なマナーについては、おおむね共通しています。
電話では顔が見えない分、声による印象が相手からの評価になります。言葉遣いを含め、失礼がないかを確認してください。
- 明るくハキハキと話す
- 不愛想な印象を与えないよう、ワントーン上の明るい声で対応する。
早口になりすぎず、ゆっくりハキハキ話すことも忘れない。
- 敬称や敬語を正しく使う
- 電話に出るときは「もしもし」は不要。
敬語の使い方や敬称を含め、相手に不快感を与えないように気をつけること。
- 電話の切り方
- 基本的に電話を受けた場合は、相手が電話を切ってから受話器を下ろす。
顧客の場合は、こちらから電話をしたケースでも相手のあとに切る。
電話をかけるとき
電話をかけるときには、以下の流れで取り次いでほしい相手がいるかどうかを確認しましょう。
- 1. 名乗り
- 社名、担当部署、担当者名を伝える
- 2. 簡潔に用件を伝える
- 要件は何かを簡単に伝える
- 3. 取次依頼
- 要件のある人がいるか(手が空いているか)を確認する
不在時や手いっぱいで対応できないと言われた場合は伝言を依頼し、要件を簡潔に伝えるようにしましょう。
また、時間のロスを省くために、要件のある相手がいつごろなら席にいるかを確認することが大切です。
テンプレート例
電話をかける際のテンプレート例は、以下のとおりです。
なおここでの取次依頼では、要件のある人がいなかった場合を想定しています。
自分:「お世話になっております。〇〇株式会社営業部の△△と申します。」
相手:「お世話になっております。」
自分:「××の件でご連絡いたしました。□□様はいらっしゃいますでしょうか?」
相手:「□□は席を外しております。」
自分:「承知いたしました。では改めてこちらからご連絡差し上げます。□□様は何時ごろにお戻りでしょうか?」
相手:「おそらく15時ごろには戻っていると思います。」
自分:「ありがとうございます。それでは15時ごろに改めてご連絡いたします。」
上記テンプレートでは、要件のある相手が何時ごろに戻るかわかっている場合です。
もし 先方でも戻る時間がわからなければ、伝言を依頼しましょう。
電話を受けるとき
電話を受けるときは、「電話をかけるとき」とは立場が逆転しただけだと思ってはいけません。
電話を受ける際には、相手の情報や要件を的確に取次先に伝達する必要があります。
また、もし相手が取り次いでほしい人物が不在の場合は、いくつか確認することもあります。
電話を受けるときは、必ずメモができる体制で応答しましょう。
誰かにメモを残す際に聞いておくべきことは、以下の4点です。
忘れずに聞き出し、メモを残しましょう。
- 電話を受けた日時
- 電話主の名前、会社名
- 要件
- 折り返しの必要性
テンプレート例
電話を受ける場合のテンプレート例は、以下のとおりです。
取次依頼の相手がいるシーンを想定しています。
自分:「はい。〇〇株式会社営業部△△が承ります。」
相手:「お世話になっております。××株式会社営業部の□□と申します。」
自分:「お世話になっております。ご用件をおうかがいします。」
相手:「◇◇の件でお電話差し上げました。失礼ですがご担当者様はお手すきですか?」
自分:「取次いたしますので、念のため再度お名前を頂戴してもよろしいでしょうか?」
相手:「××株式会社営業部の□□と申します。」
自分:「ありがとうございます。取り次ぎますので少々お待ちください。」
相手が 担当者の名前を知らない、覚えていないケースもあるので、要件をよく聞いておきましょう。
また、同じ苗字の人物が複数人いる場合はその点を相手に伝え、どちらに用事があるのか聞き返すと失礼なく取り次げます。
イレギュラーが発生したとき
電話対応は日常的に行う業務のひとつです。
当然基本だけ押さえていても、対応できないケースは存在します。
イレギュラーと呼ばれるケースですが、 この場合でも対応できるように電話対応マニュアルを作成しておくとよいでしょう。
- 相手が名乗らない場合
- つき合いが長かったり、急ぎの要件で電話をかけてきたりする場合、相手が名乗らないことがあります。
テンプレート:「恐れ入りますが、お名前を頂戴できますでしょうか?」
- 相手の声が聞こえにくい場合
- 相手の周囲が騒がしい、もしくは声が小さい場合。
まれに電波状況が悪いこともあります。テンプレート:「恐れ入りますが、お電話が少々遠いようでして……。」
「申し訳ございません、電波が悪く聞き取れませんでした。もう一度お願いします。」
- クレームを受けた場合
- 基本は聞くことに徹します。
相槌や復唱、謝辞を織り交ぜ、内容がわかれば対応を判断し行動に移しましょう。
自分で判断できない場合は保留や折り返しを活用してください。
電話での会話・応対の練習で使える例文集

ビジネスシーンにおける電話応対は、プロフェッショナルなコミュニケーションを要求される重要なスキルです。
電話の最初に言うフレーズ例は、実際のビジネスシーンで直面するさまざまな状況に合わせて、 効果的に対応するための基本的なフレーズ です。
自信を持って電話応対のスキルを磨きましょう。
- 電話を受ける場合
- 電話をかける場合
- 担当者が不在だった場合
本記事では、上記のケースで役立つ例文を紹介します。
電話を受ける場合
電話を受ける状況に相応しい応対の言葉 は、以下のようなものがあります。| 状況 | 応対 |
| 顧客からの問い合わせを受ける場合 | [会社名]の[あなたの名前]です。商品に関するご質問でございますか、それともサービスについてでしょうか? |
| 営業関連の電話を受ける場合 | [会社名]でございます、[あなたの名前]と申します。本日はどのようなご用件でしょうか? |
| 上司や同僚からの内部通話を受ける場合 | [あなたの部署]の[あなたの名前]です。 |
| 配送や注文確認のための業者からの電話を受ける場合 | [会社名]の[あなたの名前]でございます。はい、注文についての確認ですね。 |
| 不明な番号からの予期しない電話を受ける場合 | [会社名]、[あなたの名前]でございます。お電話ありがとうございます。どのようなご用件でしょうか? |
電話をかける場合
電話をかける状況に相応しい応対の言葉 は、以下のようなものがあります。| 状況 | 応対 |
| 顧客へ商品やサービスの意見を聞くために電話をかける場合 | [顧客名]様、こんにちは。[会社名]の[あなたの名前]と申します。先日ご利用いただいた[商品/サービス名]について、お客様のご意見を伺いたくお電話させていただきました。 |
| 取引先企業に新しい提案やプロジェクトについて話をするために電話をかける場合 | [取引先企業名]の[担当者名]様、[あなたの会社名]の[あなたの名前]でございます。本日は新しい提案についてお話しさせていただきたくお電話いたしました。 |
| 社内の同僚や上司にプロジェクトの進捗状況を報告するために電話をかける場合 | [あなたの名前]です。[プロジェクト名]の進捗状況についてご報告させていただきたいのですが、少々お時間いただけますでしょうか? |
| 問い合わせに対する回答や解決策を伝えるために電話をかける場合 | [顧客名]様、[会社名]の[あなたの名前]です。先日いただいたご質問について、解決策をご提案させていただきたくお電話しました。 |
| 注文の確認や変更の依頼をするために電話をかける場合 | [業者名]の[担当者名]様、[あなたの会社名]の[あなたの名前]でございます。先日の注文について、確認事項がございますので、少しお時間いただけますでしょうか? |
担当者が不在だった場合
担当者が不在だった状況に相応しい応対の言葉 は以下の通りです。| 状況 | 応対 |
| トイレで席を外していた場合 | 申し訳ございません、[担当者名]はただいま席を外しております。お急ぎでしたらメッセージをお伝えすることもできますし、後ほど折り返しお電話させますが、どちらがよろしいでしょうか? |
| 体調不良で欠席している場合 | [担当者名]は本日体調不良のため欠席しております。ご用件をお伝えいただければ、メモを取らせていただきます。または、回復次第、折り返しご連絡させます。 |
| 会議中の場合 | 現在[担当者名]は会議中でして、お電話に出られません。会議終了後、折り返しお電話させますが、お待ちいただけますでしょうか? |
| 帰宅した後の場合 | [担当者名]は本日の業務を終え、すでに帰宅しております。明日改めてご連絡させますが、よろしいでしょうか? |
| リモートワークの場合 | [担当者名]は現在リモートワーク中です。メールにてご連絡させていただくか、後ほどお電話させますが、どちらがご都合よろしいでしょうか? |
電話対応がうまい人の特徴

電話対応がうまい人には、以下のように共通する特徴があります。
- 丁寧な言葉遣い
- 相手が聞き取りやすい声
- 情報を伝えるのがうまい
上記の特徴を身につけることで、どのような電話応対もスムーズかつプロフェッショナルにこなせるようになります。
丁寧な言葉遣い
電話対応のうまい人は、常に 丁寧な言葉遣い を心がけています。
丁寧な言葉は相手に敬意を示し、良好なコミュニケーションの基盤を築くことに貢献します。
また、丁寧な言葉遣いによって、顧客や取引先との信頼関係が深まり、長期的なビジネス関係の構築に役立つでしょう。
例えば、電話応対時に「お世話になっております」「ありがとうございます」といった表現を使うことは、相手に対する礼儀を示すと同時に、プロフェッショナルな印象を与えます。
丁寧な言葉遣いは、電話対応の質を高め、相手にいい印象を与えるために必要不可欠な要素です。
丁寧な電話応対を心がけることで、 プロフェッショナルなビジネスパーソンとしての信頼を築きましょう。
相手が聞き取りやすい声
電話対応がうまい人は、 相手が聞き取りやすい声 を意識しています。
聞き取りやすい声で話すことで、相手は情報を正確に理解しやすくなり、コミュニケーションがスムーズに進みます。
受け手は、明瞭な発音と適切な速度で話されると、安心感を持ち、話し手に対して好印象を抱くでしょう。
聞き取りやすい声の特徴は以下の通りです。
- はっきりとした発音
- 適度な声量
- 遅すぎず早すぎない話し速度
上記を意識することで、電話の向こう側にいる相手に対して情報を明確に伝えられます。
情報を伝えるのがうまい
電話対応がうまい人は、 情報を伝えるのが得意 です。
情報を伝えるのがうまいと、相手に対して必要な情報を明確かつ効率的に伝えられるので、受け手は話し手に対して信頼感を覚え、伝えられた情報を簡潔に理解しやすくなります。
情報をうまく伝える人の特徴は以下の通りです。
- 要点を抑えている
- 余分な情報を省略している
聞き手の理解度を考慮しながら、ポイントを明確にし、わかりやすい言葉を用いて伝えます。
情報をうまく伝える能力は、 誤解を防ぎ効率的な意思疎通が可能となる ので、全体的なビジネスの進行においてもプラスの影響を与えます。
自信を持って電話対応を行うために

電話対応では、 失礼のない言葉遣いはもちろんのこと、自信を持って対応する必要があります 。
自信のなさは声に乗って、相手に伝わってしまうでしょう。
自信を持った電話対応を行うためには、以下の3点に気をつけるようにしましょう。
- マニュアルを読み込む
- 丸暗記をする必要はありませんが、見なくても基本的な流れがわかる程度に読み込むと、おどおどした対応にならないためおすすめです。
- ロールプレイを行う
- 社内でロールプレイを実施し、場数を踏む機会を意図的に作りましょう。
相手役が上司や先輩の場合は、同時にフィードバックを受けるのもおすすめです。
- 明るく大きな声で話す
- とにかく明るく大きな声で話すと、自信のなさが伝わりにくくなります。
また、早口にならないように意識的に、話のテンポも緩めるといいでしょう。
電話対応マニュアル作成|関連周辺お役立ち無料資料・記事

電話対応に困っている方々に、以下の 電話対応マニュアルの作成時に役立つ無料資料・記事 をまとめてみました。
- 電話業務お悩み解決Book
- アポ率を2.6倍伸ばす実践的トークテクニック全集
- コールセンターで使える言葉遣い一覧
概要を以下にまとめてみました。
気になるマニュアル・記事があれば、ぜひ参考にしてみてください。
電話業務お悩み解決Book
「電話業務お悩み解決Book」では、 受電業務の悩みと具体的な解決手法 を合わせて公開しています。
| 資料の内容 | こんな人におすすめ |
|
|
アポ率を2.6倍伸ばす実践的トークテクニック全集
「アポ率を2.6倍伸ばす実践的トークテクニック全集」では、 アポ率を上げるノウハウとトーク術 を公開しています。
| 資料の内容 | こんな人におすすめ |
|
|
コールセンターで使える言葉遣い一覧
「コールセンターで使える言葉遣い一覧|NGな言葉遣いも紹介」では、 マニュアルの作成時にも活用できる言葉使い をリスト化してまとめております。
| 記事の内容 | こんな人におすすめ |
|
|
まとめ
電話対応マニュアルを作れば、全社で電話の品質を一定にできます。
声音やテンションは練習あるのみですが、 電話に出る全員が同じように対応できるのは企業としての強みです 。
作り方がわからず放置してきた人は、この機会に電話対応マニュアルの作成を検討してください。
しかし、いざ実践になると練習どおり話せない人もいるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、Scene Liveのインバウンド・アウトバウンドコールシステム「List Navigator.」と「OSORA」です。
通話録音やささやき機能など、電話対応を改善・支援できる機能が搭載されています。
マニュアル作成や改善に役立つ上、業務効率化もできるサービスです。
電話対応の教育をしながらマニュアルの作成・ブラッシュアップしたい方は、ぜひ導入を検討してください。
■合わせてよく読まれている資料
「営業効率をアップさせるトークスクリプト作成法」も合わせてダウンロードいただけます。









