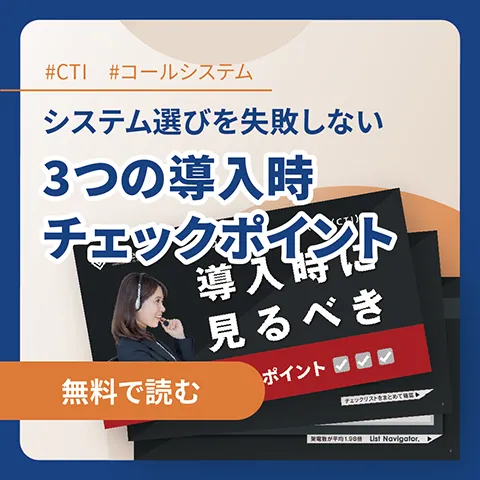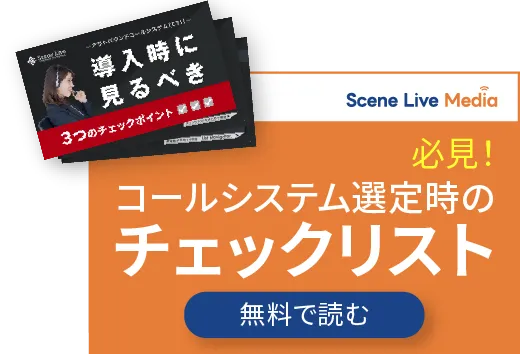- 営業テック
- 2025.08.28
CTI連携とは?仕組み・メリット・連携できるシステムを解説

近年、顧客対応のデジタル化が加速し、電話業務においても迅速かつ的確な対応が求められるようになっています。その中で注目を集めているのが「CTI連携」です。
CTI(Computer Telephony Integration)は、電話とコンピューターを連携させる技術で、CRMやSFA、PBXなどの各種システムと組み合わせることで、業務効率の向上や顧客満足度の向上につながります。
この記事では、 CTI連携の仕組みやメリット、連携すべき代表的なシステム、導入時の注意点 までをわかりやすく解説します。
CTIとCRMの連携を考えている人は、ぜひ本記事を参考にしてください。
CTIとは?複数システムとの連携が可能になった背景
CTIは、電話とコンピュータを連携させる技術です。
電話とコンピューターを連携させることで、以下のようなさまざまな機能を活用でき、電話業務の効率化が実現します。
【代表的な機能】
・着信時に顧客情報を自動でポップアップ表示
・コンピューター画面から直接発信
・通話内容や対応履歴を記録・分析
これらの機能により、 架電・受電に関わるスタッフの業務負担が軽減されるほか、通話内容をもとにしたフィードバックや教育が可能になり、スタッフのスキル向上に活かす こともできます。
かつては電話回線とコンピューター回線の仕組みが異なり、このような機能を活用することはできませんでしたが、デジタルテクノロジーが進化したことで技術的な障壁がなくなり、多種多様な機能を提供するCTIが登場しました。
また、電話回線とコンピューター回線だけでなく、 異なるシステム同士を連携させる技術も進化し、現在ではCTIに多様なツールを連携させることもできるようになりました 。
「複数のシステムを同時に利用することの負担や非効率性」は、多くの企業の課題となっており、複数のツールやシステムと連携できるCTIは非常に人気が高くなっています。
CTIと連携できる主なシステム
では、CTIと連携できる主なシステムとしては何があるのでしょうか?ここでは、CTIとの連携が可能な6つのシステムをご紹介します。
- CRM(顧客管理システム)
- PBX・クラウドPBX
- SFA(営業支援システム)
- チャットボット
- FAQシステム
- 音声認識・テキストマイニング
CRM(顧客管理システム)
CRM(Customer Relationship Management)は、顧客情報を一元管理するシステムです。
CTIと連携することで、 着信時に顧客情報を自動ポップアップ表示でき、オペレーターは架電や受電業務の際に顧客情報を確認しながら最適な提案が可能 になります。
また、通話内容や対応履歴はCRMに自動記録され、分析やマーケティング活動にも活用できます。これにより、顧客との関係性強化や顧客満足度向上が期待できます。
PBX・クラウドPBX
PBX(Private Branch Exchange)は、社内の内線管理や着信振り分けを行うシステムです。
CTIと連携することで、 部門別・担当者別の自動振り分けや、スムーズな転送、電話履歴の一元管理 を行えます。
CTIとクラウドPBXを組み合わせれば、インターネット経由での通話管理ができるため、在宅勤務や拠点間連携にも柔軟に対応できます。
SFA(営業支援システム)
SFA(Sales Force Automation)は、営業活動を効率化するための支援システムです。
CTIとの連携により、 通話中に商談状況や提案履歴を確認でき、顧客ごとのアプローチ方法を事前に把握したうえで営業やテレアポに臨むことができます 。
これにより、営業活動の属人化を防ぎ、成果につなげやすい営業体制を構築できます。
チャットボット
チャットボットは、テキストベースでの自動応対を行うシステムで、顧客対応をメインとするインバウンド業務で主に活用されています。
CTIと連携すると、 チャット対応から通話対応へのシームレスな引き継ぎが可能になり、スタッフやオペレーターはチャット履歴を確認しながら通話できるため、応対がスムーズ になります。
顧客にとっても状況説明の繰り返しが不要になり、ストレスの少ないサポート体験を提供できます。
FAQシステム
FAQシステムは、よくある質問と回答をデータベース化して管理できるツールで、チャットボットと同様に主にインバウンド業務向けのシステムです。
CTIと連携することで、 スタッフやオペレーターは通話中にマニュアルやFAQを瞬時に検索でき、対応スピードを向上 させられます。
さらに、スタッフごとにカスタマイズ可能な検索機能や、事後処理時間の短縮など、応対効率を高める多様な機能が搭載されています。
音声認識・テキストマイニング
音声認識機能は、通話内容をリアルタイムでテキスト化し、対応履歴を自動整理してくれるシステムです。
さらに、 テキストマイニング技術を使えば、キーワード抽出や感情分析が可能となり、通話品質や課題を可視化 できます。
これらのデータはスタッフ教育やFAQ改善にも役立ち、継続的なサービス品質向上につながります。
ここでご紹介したのは、CTIと連携できる代表的なシステムですが、API(※異なるシステム同士を接続するための仕組み)を公開しているCTIであれば、 特別なカスタマイズや大規模な仕様変更をせずにシステム連携が行えます 。
連携実績のない多種多様なシステムと連携したいという場合は、APIを公開しているCTIを選ぶとよいでしょう。
CTIとシステムの連携によって得られるメリットは?
CTIと各システムを連携するメリットはさまざまです。
ここでは、CTI連携によって得られる主なメリットをご紹介します。
- 情報の一元化による業務効率化
- 既存の顧客管理方法を変える必要がない
- 顧客対応の迅速化と満足度向上
- 従業員の負担軽減・柔軟な働き方
情報の一元化による業務効率化
CTIと各ツールの連携ができなかった時代は、顧客情報の確認作業、電話発信、電話後の情報入力作業など、複数の業務を別々のツールを立ち上げて行う必要がありました。
CTIと各ツールの連携が可能になると、 同じ管理画面から「確認・発信・入力」といった業務を行えるようになり、業務効率を大幅に向上 できます。
既存の顧客管理方法を変える必要がない
CTI導入にあたり、新しい管理方法への切り替えが必要になるケースもありますが、既存のシステムと連携できるCTIを選べば、切り替える必要はありません。
現在の顧客情報や運用フローを維持したまま、 CTIによる効率化や応対品質の向上を図ることが可能になり、導入にかかるコストや負担を最小限に抑えつつCTIによるメリットを得られます 。
顧客対応の迅速化と満足度向上
CRMとCTI連携すれば、アウトバウンドの場合は 「顧客情報などを確認しながら、顧客にアプローチできる」インバウンドの場合は「着信と同時に顧客情報をポップアップ表示でき、本人確認や初期ヒアリングの手間を省ける」 などのメリットがあります。
また、SFAとCTIを組み合わせれば、過去のやり取りや商談履歴を確認しながら会話を進められ、よりスムーズな提案が可能です。購入履歴や問い合わせ内容をもとに、顧客ごとに最適な案内を行えるため、満足度の向上にもつながるでしょう。
従業員の負担軽減・柔軟な働き方
オートコールやプレディクティブコール機能を搭載したCTIを導入することで、 発信作業や着信対応にかかる工数を削減でき、スタッフの負担を軽減できます 。
また、CRMやSFAなどのツールと連携することで、情報の確認・入力といった作業もスムーズになり、電話業務に関わるさまざまな業務の負担を軽減できます。
インバウンド業務の場合は、クラウドPBXなどのツールと連携することで、スマートフォンによる着信や在宅での通話対応も可能になり、働き方の多様化や柔軟化につなげることができます。
CTIとシステムの連携を成功させるポイントは?
CTIとその他のシステムの連携を円滑かつ効果的に進めるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
ここでは、導入前に押さえておくべき4つのポイントを解説します。
- 必要な機能を洗い出しておく
- 既存システムとの互換性を確認する
- セキュリティ対策とサポート体制を確認
- 社員教育を徹底する
必要な機能を洗い出しておく
CTI連携を検討する最初のステップは、「何を実現したいのか」「そのためにどの機能が必要なのか」を明確にすることです。
導入後に機能不足や使い勝手の不一致が発覚しないよう、 自社の業務フローや顧客対応における課題を整理し、それに適した機能を選定する 必要があります。
必要な機能は業種や部門、顧客層によって異なるため、現場のヒアリングや業務プロセスの可視化を行い、優先順位をつけて検討することが重要です。
既存システムとの互換性を確認する
CTIが高機能であっても、既存のCRM、SFA、ERPなどと連携できなければ、データの手入力や二重管理が発生し、かえって非効率になる恐れがあります。
導入前には、 既存システムとスムーズに連携できるかを必ず確認しましょう 。可能であればベンダーに自社環境の詳細を共有し、事前に技術的な実現可能性を検証することで、導入後のトラブルを防げます。
セキュリティ対策とサポート体制を確認
CTI連携では、通話内容や顧客の個人情報、営業機密などの重要データを扱うため、セキュリティ対策は欠かせません。
特にクラウド型システムでは、インターネット経由で情報をやり取りするため、 通信の暗号化(TLS/SSL)、アクセス権限の管理、IP制限・二段階認証、データ保存場所・ログ管理などの安全対策を確認しましょう 。
また、導入後の運用サポートやトラブル時の対応体制も重要です。 24時間対応の有無、障害発生時のリカバリ体制、FAQやユーザーコミュニティの有無 など、安心して運用できる環境が整っているかを事前にチェックしておきましょう。
社員教育を徹底する
CTI連携による効果を最大限に発揮するためには、現場の社員がシステムを正しく使いこなせることが不可欠です。
「機能はあるのに使われていない」「誤操作が多い」といった事態を避けるため、計画的な教育プログラムを用意 しましょう。また、応答率や平均対応時間といったKPIを定期的に可視化することで、社員のモチベーション向上や改善意識の定着につながります。
主要ツールとのスムーズな連携が可能!lisnavi(リスナビ)とは?
アウトバウンド業務でのCTI連携を検討している方には、株式会社Scene Liveが提供するクラウド型CTI「lisnavi(リスナビ)」の導入がおすすめです。
lisnaviには CRM連携やAPI連携機能が搭載されており、既存の顧客管理体制を維持したままCTIをスムーズに導入 できます。
また、オートコールで繋がるまでの工数を自動化する機能や、リスト・スタッフ・成績を1画面で管理・分析できるダッシュボード機能を搭載しており、架電業務の課題解決に優れています。
| 提供形態 | クラウド型 |
|---|---|
| 業務形態 | アウトバンド |
| 主な機能 |
・オートコール ・再コール ・グループ発信 ・クイック発信 ・ワンクリック発信 ・トークスクリプト共有 ・スタッフ分析 ・ダッシュボード ・リスト別分析 ・ステータス分析 ・架電時間分析 ・複数プロジェクト管理 ・CSVインポート・エクスポート ・事前情報管理 ・見込みステータス管理 ・モニタリング ・ウィスパー(ささやき) など |
| 費用 | 月額5,000円 /ブース から |
| URL | 【公式】lisnavi(リスナビ)|旧:List Navigator. |
また、 ブース数、つまり同時稼働する人数に基づいた課金形態を採用している点もメリット です。例えば、50人がシステムを使う場合も、同時稼働人数が最大10人であればご請求は10人分のみ。
アルバイトやパートのスタッフも多い企業では、ID課金のシステムからブース課金のシステムに変更することで大幅なコスト削減も期待できます。
アウトバウンド型システムのリスナビを詳しく知りたい方は、lisnaviのサービス資料をご覧ください。
システム連携でCTIの利便性を高める
CTIは、各業務効率化システムと連携することでさらに高い効果を発揮します。
とはいえ、システム連携が可能なCTIにもさまざまな種類があるため、どれを選ぶべきか迷ってしまうかもしれません。
導入形態や機能、セキュリティなど、選び方のポイントを押さえた上で、自社に合うものを見つけましょう。
特にCTIを検討している場合は、 アウトバウンドならlisnavi(リスナビ)が、インバウンドならOSORAがおすすめ です。
どちらも機能が充実しており低コストで導入できるため、自社の業務に合わせより適している方を検討してください。
|
■アウトバウンド特化のコールシステム lisnavi(リスナビ) lisnavi(リスナビ)は、累計導入社数2,700社(2025年7月時点)を誇る、株式会社Scene Liveが販売するCTIシステムです。
などなど、電話業務の課題解決に優れています。 さまざまな業務・現場の需要に対応する柔軟性・カスタマイズ性を兼ね備えたCTIシステムです。 柔軟性や効率性に優れたアウトバウンド向けCTIをお探しの方は、ぜひこちらから詳細をご確認ください。 |

-
Written by株式会社Scene Live マーケティング部
コラム・セミナー・お役立ち資料を通して、電話業務や営業活動を効率化させる実践的な情報を配信しています。ツールの使い方や業界の動向など、最新情報を発信し続けることで電話業務に携わるすべての人にとって信頼できる情報源になることを目指しています。
COLUMN合わせて読まれているコラム