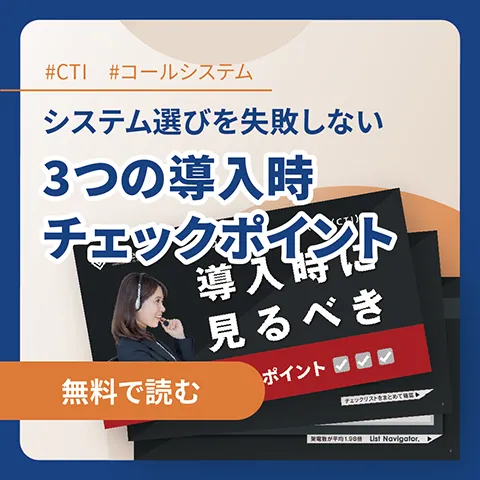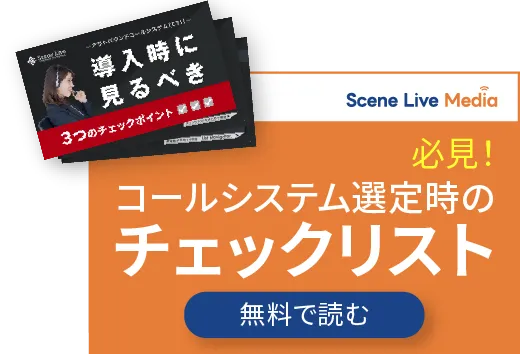- 営業テック
- 2025.08.28
CTIとPBXの違いは?仕組みや連携の構成図について解説

CTIやPBXの特徴や違いをご存知でしょうか。
CTIはコールセンター業務の効率化や人件費などのコスト削減など様々な恩恵をもたらすシステムです。
一方でPBXとはどういったものか、CTIとの違いや仕組みがわからないという方もいるのではないでしょうか?
この記事では、 CTIとPBXの違いをわかりやすく解説します 。業務効率化のシステム導入を考えている場合は導入のための参考にしてください。
CTIとPBXの違いとは

CTIとPBXの仕組みについて、順に解説していきます。
- CTIはコンピュータと電話を統合するための仕組み
- PBXは電話回線に関する仕組み
関連記事:PBXとは?レガシー・IP・クラウドそれぞれのメリットとデメリット
CTIはコンピュータと電話を統合するための仕組み
CTI(Computer Telephony Integration)は、コールシステムを構成する重要な要素のひとつで、コンピュータと電話をつなぐ仕組みです。
電話回線とコンピュータシステムを連携させることで、 FAXやクラウドPBX(構内交換機)、CRM(顧客管理システム)など、さまざまなシステムとの統合が可能 になり、電話業務の効率化を実現する以下のような機能を提供します。
・オートコール:あらかじめ設定した架電リストに沿って自動発信を行う機能
・トークスクリプト:通話中に案内すべき内容や質問事項を画面上に表示する機能
・リスト管理:架電リストや顧客情報を効率的に整理・活用する機能
・ささやき機能:通話中のオペレーターに管理者が指示やアドバイスを送る機能
これらの機能は、単体のコンピュータや従来型のPBXだけでは実現が難しいものですが、CTIを導入することで活用でき、 通話業務の効率化、対応品質の向上、顧客満足度の改善などを同時に実現 できます。
関連記事:CTIとは?基本機能や種類・導入のメリット・デメリットをわかりやすく解説!
PBXは電話回線に関する仕組み
PBX(Private Branch eXchange)は、コールシステムを構成する要素のひとつで、社内の電話回線を効率的に管理・制御するための仕組みです。
従来は社内に専用の機器を設置し、内線と外線の接続や、内線同士の接続をコントロールしていましたが、PBXが導入されたことで、以下のような機能を利用できるようになりました。
- ダイヤルイン機能:1本の外線着信を複数の内線番号に振り分ける
- 保留機能:通話を保留し、別の電話機で受け直せる
- 転送機能:不在時に別の電話機や番号へ自動的に転送する
これらの機能により、 企業内でのスムーズな通話のやり取りや、顧客対応の効率化が可能 になります。
近年では、 PBX機器を設置せず、クラウドを通じて同様の機能を提供するクラウドPBXが普及 しています。
クラウドPBXは、場所やデバイスを問わず利用できるため、在宅勤務や拠点間連携にも柔軟に対応できるのが大きな特徴です。
CTIとPBXの違いは?
CTIとPBXはいずれもコールシステムを構成する要素です。
より細かく説明すると、近年販売されているCTIにはPBX機能が搭載されていることが多く、CTIの方がより包括的な役割を担っています。
ただ、CTIは「パソコンと電話機を接続する」、PBXは「電話回線を制御する」という明確な機能の違いがある点は抑えておきましょう。
| CTI | PBX | |
|---|---|---|
| 役割 | 電話とパソコンのほか、CRMやSFAなどのビジネスツールと連携する | 社内の外線・内線を効率的に管理・制御する (※CTIの機能のひとつに含まれる) |
| 主な機能 | ・オートコール ・リスト管理 ・トークスクリプト ・ささやき機能 ・CRM連携 など |
・ダイヤルイン機能 ・保留機能 ・転送機能 など |
PBXとCTIは同時に活用するもの
PBXとCTIは役割が異なるものの、連携させることで大きな効果を発揮します。
PBXは電話回線を制御する仕組みで、内線・外線の接続や着信振り分けなどを担います。一方、CTIは、電話とコンピューターを統合し、他のシステムと連携させるためのシステムです。
PBXとCTIをバラバラに利用するのではなく、近年では同時に活用できるように設計されており、 PBX機能を搭載したCTIを利用することで、通話録音やモニタリングなど、多彩な機能を活用 できるようになります。
これにより、電話業務の効率化だけでなく、スタッフの教育や品質向上といった人材育成の場面でも活躍します。
さらに、種類によってはCTIはCRM(顧客情報の管理システム)やSFA(営業活動の支援システム)といったシステムとも連携できます。
たとえば、CRMとCTIを繋げば、着信と同時に顧客情報をPC画面に表示でき、スタッフはスムーズかつ的確な応対が可能になります。
このように、 PBXをはじめとする複数のシステムが結合されたCTIを導入することで、利便性の高いコールシステムを構築 でき、業務効率と顧客満足度の両立が実現します。
PBXとCTIの導入で得られるメリットは
PBX・CTIを導入することで、電話業務の効率化やデータ活用、働き方の柔軟化など、さまざまなメリットが得られます。代表的な効果としては以下の3点が挙げられます。
- 業務効率が高まる
- データの集積・分析・活用が可能に
- 電話業務のリモート化が可能に
業務効率が高まる
PBXとCTIを導入すると、コールセンターやオフィスにおけるオペレーター業務の効率化が可能になります。
多くの発信・着信を効率的にコントロールできるほか、自動着信振り分け機能や、CRMとの連携による顧客情報の自動表示にも対応できます。
これにより、 未導入の状態に比べてスタッフの負担が大幅に軽減され、業務スピードも向上 します。
このような効率化によって人的コストの削減も可能になり、空いたリソースを別業務に活用するか、人員を適正化するかなど、柔軟な運用判断ができるようになります。
データの集積・分析・活用が可能に
CTIの録音機能や通話履歴機能などを活用することで、 日々の電話対応から得られるデータを業務改善に活かすことができます 。
たとえば、録音した顧客の声をテキスト化し社内で共有すれば、顧客アンケートや市場調査を行わなくても、顧客ニーズの把握や営業戦略の立案に活用できます。
PBXとCTIはマーケティングや営業活動の精度を高める情報基盤としても有効なのです。
電話業務のリモート化が可能に
クラウド型PBX・CTIの導入は、電話業務のリモート化推進にも効果的です。
PBXを搭載したクラウド型CTIを導入することで、 スタッフは自宅のパソコンからでもシステムにアクセスできるようになり、自宅から電話の受発信に対応 できるようになります。
専用のテレワークシステムを新たに構築する必要がなく、遠隔地からでも通常業務を継続できるため、「在宅勤務なら働き続けられる」という人材の離職防止にもつながります。
こうした柔軟な働き方を支援する取り組みを進めたい企業にとっても、PBXとCTIの導入は有効な選択肢です。
PBXとCTIの選び方は?
PBXやCTIを導入する際は、製品の種類や機能だけでなく、既存システムとの相性やサポート体制など、複数の観点から比較・検討することが重要です。ここでは、選定時に押さえておきたい、以下の5つのポイントを解説します。
- 目的に合わせて種類を選ぶ
- 必要な機能がそろっているか
- 既存システムとの相性や連携
- 機能のカスタマイズは可能か
- セキュリティ・サポート体制は整っているか
目的に合わせて種類を選ぶ
PBXやCTIには「オンプレミス型」と「クラウド型」があります。
オンプレミス型は、自社内にサーバーを設置し、システムをいちから構築する方法で、自社の求める機能やセキュリティレベルに合わせてカスタマイズできるのが特徴です。
クラウド型は、ベンダーが構築したシステムにアクセスする方式で、 インターネット回線さえあれば利用でき、サーバー設置が不要で初期費用も抑えられます 。運用の柔軟性やコスト面から、近年はクラウド型が主流となっています。
通常のクラウドCTIには搭載されていない特殊な機能が必要な場合はオンプレミス型、導入・運用コストを抑えて短時間で導入したい場合はクラウド型など、目的に合わせてシステムを選びましょう。
必要な機能がそろっているか
導入目的や解消したい課題に応じて、必要な機能が搭載されているかを確認しましょう。
たとえば、テレアポやアンケート調査などのアウトバウンド業務の方は、発信効率を高めるオートコールや提案内容の属人化を防げるトークスクリプト共有機能など、 自社が抱える課題に合わせて必要な機能が搭載された製品を選ぶことが大切 です。
事前に必要機能のリストを作成し、候補製品の機能と照らし合わせて比較検討することが大切です。
既存システムとの相性や連携
CRMやSFAなど、 現在使用している業務システムとの連携面や相性の良さも確認 しましょう。
また、既存の電話回線との接続が可能かどうかなど、必要な場合はハード面も合わせて確認し、導入後にトラブルが発生しないように注意しましょう。
また、API連携やデータ連携が可能であれば、既存環境を活かしたままスムーズに導入でき、移行後のトラブルも減らせます。
機能のカスタマイズは可能か
自社の業務フローに合わせたカスタマイズが可能かどうかも重要なポイントです。
自社に合わせてカスタマイズが必要な場合はオンプレミス型の導入が必要でしたが、 最近ではカスタマイズが可能なクラウド型のシステムも増えており、機能追加や拡張が可能なケースが増えています 。
「クラウド型を希望しているが、機能追加や拡張がしたい……」といった課題がある場合は、カスタマイズに対応できるか?カスタマイズに必要な期間はどの程度か?などをベンダーに確認しましょう。
業務や組織の変化に柔軟に対応できる製品を選ぶことで、長期的な運用に適した環境が構築できます。
セキュリティ・サポート体制は整っているか
PBXやCTIは、 通話データや顧客情報を扱う以上、強固なセキュリティ対策が必要不可欠 です。
そのため、セキュリティ機能を自社でカスタマイズできないクラウド型を選ぶ場合は、暗号化通信やアクセス制限、データ保管体制などが整っているかを確認しましょう。
また、導入後のサポート体制も重要で、 問い合わせ対応のスピード、障害発生時の復旧体制、24時間対応の有無などを事前に把握しておくことが、安心した運用につながります 。
CTIシステムの導入、PBXとの連携で業務を効率化しよう

CTIとPBXの違いから仕組み、導入によって得られるメリットについて紹介しました。
CTIとPBXはそれぞれ個別に語られる機能ですが、 実際にはPBXはCTIに含まれる機能の一部であり、同時に活用することで効果を発揮 します。
コールシステムの改善のため、PBXやCTIの導入やリプレイスを検討している方は、今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。
なお、コールセンター業務を自社で行いたい場合には、 Scene Liveが提供しているインバウンド向けコールセンターシステムの「OSORA」と、アウトバウンド向けコールセンターシステムの「lisnavi(リスナビ)」 の導入をご検討ください。
両製品とも機能が充実しており、コールセンターの業務効率化に役立ちます。
Scene Liveの製品は、 累計3,200社(2025年7月時点)の導入実績を記録し、多くの企業でご利用いただいている信頼性の高いシステム です。
|
■アウトバウンド特化のコールシステム lisnavi(リスナビ) lisnavi(リスナビ)は、累計導入社数2,600社(2025年7月時点)を誇る、株式会社Scene Liveが販売するCTIシステムです。
などなど、電話業務の課題解決に優れています。 さまざまな業務・現場の需要に対応する柔軟性・カスタマイズ性を兼ね備えたCTIシステムです。 柔軟性や効率性に優れたアウトバウンド向けCTIをお探しの方は、ぜひこちらから詳細をご確認ください。 |

-
Written by株式会社Scene Live マーケティング部
コラム・セミナー・お役立ち資料を通して、電話業務や営業活動を効率化させる実践的な情報を配信しています。ツールの使い方や業界の動向など、最新情報を発信し続けることで電話業務に携わるすべての人にとって信頼できる情報源になることを目指しています。
COLUMN合わせて読まれているコラム