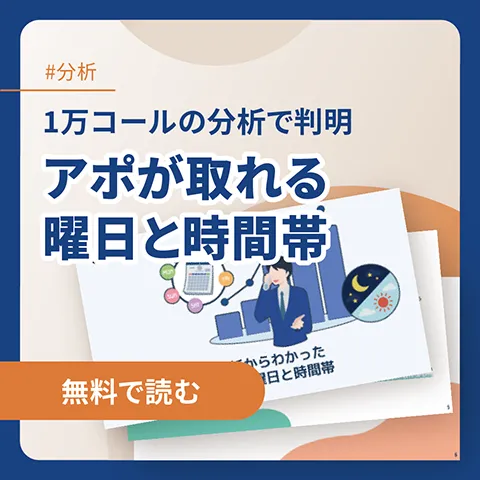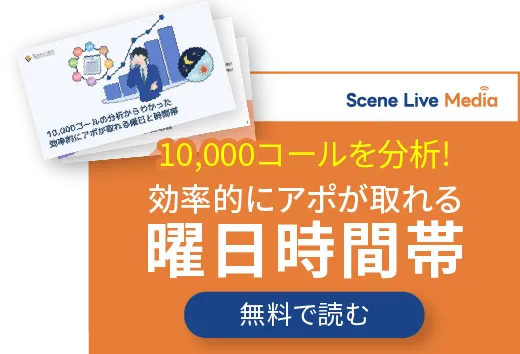- アポ率UP
- 2025.07.17
営業電話・テレアポが効果的な時間帯|個人・法人別、マナーや違法範囲は?

営業電話・テレアポにおいて、話を聞いてもらいやすい時間帯はいつなのでしょうか。
「昼休みの時間帯は電話するのを避けるべきなのか」「マナー違反となる時間帯はあるのか」と迷う方も少なくないでしょう。
本記事では、営業電話の時間帯に関して以下の内容を解説します。
- 法人への営業電話が効果的な時間帯
- 個人への営業電話が効果的な時間帯
- 営業電話が効果的な曜日
- 営業電話がマナー違反・違法となる時間帯
さらに、営業電話がつながらない場合の対処法に関しても解説しているので、営業電話で成功率を上げたい方はぜひ参考にしてください。
個人への営業電話が効果的な時間帯

もちろん、電話をかける相手によってつながりやすい時間帯は変わります。
勤務時間後
営業電話の相手が出社して仕事をする人の場合、勤務時間後を狙って電話をかけるとよいでしょう。
勤務中は、個人の電話に出られないことがあるためです。
仕事を終えて帰宅すると考えられる 17~19時を目安に電話をかけましょう 。
ただし、在宅勤務をする会社員の場合は、勤務時間中であっても電話がつながる可能性があります。
昼〜夕方
営業電話の相手が長時間自宅にいる場合は、昼~夕方の時間帯なら電話がつながりやすいです。
例えば、 主婦に電話をかける場合は、家事が忙しくなる時間を避けた昼過ぎから夕方だと電話がつながりやすいでしょう 。
個人向けの営業電話は柔軟に
ご紹介したように、対象が個人の場合は「平日の時から17~19時」「週末の13~17時」がおすすめの時間帯ですが、個人のライフスタイルはさまざまです。
仕事の種類や家族構成、年代、性別によって、電話に出やすい時間や曜日が変わるため、 まずは推奨したタイミングで電話をかけ、都合が悪そうなときは対応しやすい曜日や時間を確認して電話を切ります 。
一度目の電話は電話をかけやすい時間を確認する目的と割り切り、2回目以降で提案やアポイントにつなげる意識で電話をかけてもよいでしょう。
法人への営業電話・テレアポが効果的な時間帯

法人への営業電話・テレアポは、 基本的に午前中と夕方の時間帯が効果的です 。
これらの時間帯に電話をかけると、話を聞いてもらえる確率が高いといわれています。
その理由をそれぞれ以下で解説します。
ただし、業種によっては効果的な時間帯が異なるため注意が必要です。
関連記事:法人向けテレアポを成功させるコツ|上手くいかない原因から徹底分析
午前中
1つ目の効果的な時間帯は午前中です。
理由は、担当者がメール処理などの内勤業務を行っていることが多いためです。
また、午前中は外回りが多い担当者と直接話せる可能性が高い時間帯ともいえます。
具体的には、 10~11時半を目安に電話をかけるとよいでしょう 。
ただし、始業時間の直後は朝礼などで電話に出られないことが想定されるため、避けるべきです。
午前中に電話で話ができれば、予約を取り付けて午後に訪問できる場合もあります。
夕方
2つ目の効果的な時間帯は夕方です。
重要な会議や商談が終わり、担当者の仕事が一段落することが多いためです。
具体的には、 14~16時を目安 にするとよいでしょう。
担当者が仕事の息抜きをしたいタイミングに合わせて電話をかけると、じっくり話を聞いてもらえる可能性が高まります。
なお、終業時間の間際に営業電話をするのは避けましょう。
担当者が帰宅の準備に取り掛かるため、電話対応を嫌う可能性が高いと考えられます。
業種によって効果的な時間帯がある
業種によって、テレアポが効果的な時間帯は異なります 。代表的な業種と効果的な時間帯は、以下の通りです。
| 業種 | 時間帯 |
| 一般企業 | 10~11時半 14~16時 |
| 飲食業 | 11時前 14~17時 |
| 病院 | 8時頃 12時頃 |
| 不動産業 | 10時前 |
| 美容室・理容室 | 10時前 |
| 教育業界 | 15~17時 |
| 工場 | 16~17時 |
飲食業はランチやディナーの営業時間を避けた時間帯がよいでしょう。
病院は診療時間を避けて電話をかけると、話を聞いてもらえる確率が高まります。
また、不動産業や美容室・理容室は接客業務で忙しくなる時間帯の前に電話をかけるとつながりやすいでしょう。
教育業界は、授業などの関係で夕方までは電話に出られない可能性が高いため、夕方を狙って電話をかけましょう。工場関係は、ライン作業がひと段落する16~17時ごろを狙うのがおすすめです。
なお、これらの時間帯はあくまで目安のため、必ず対応してくれるとは限りません。
電話に出てくれたものの時間がなさそうなときは、対応可能な曜日や時間を聞き、手短に電話を切りましょう。営業電話・テレアポが効果的な曜日
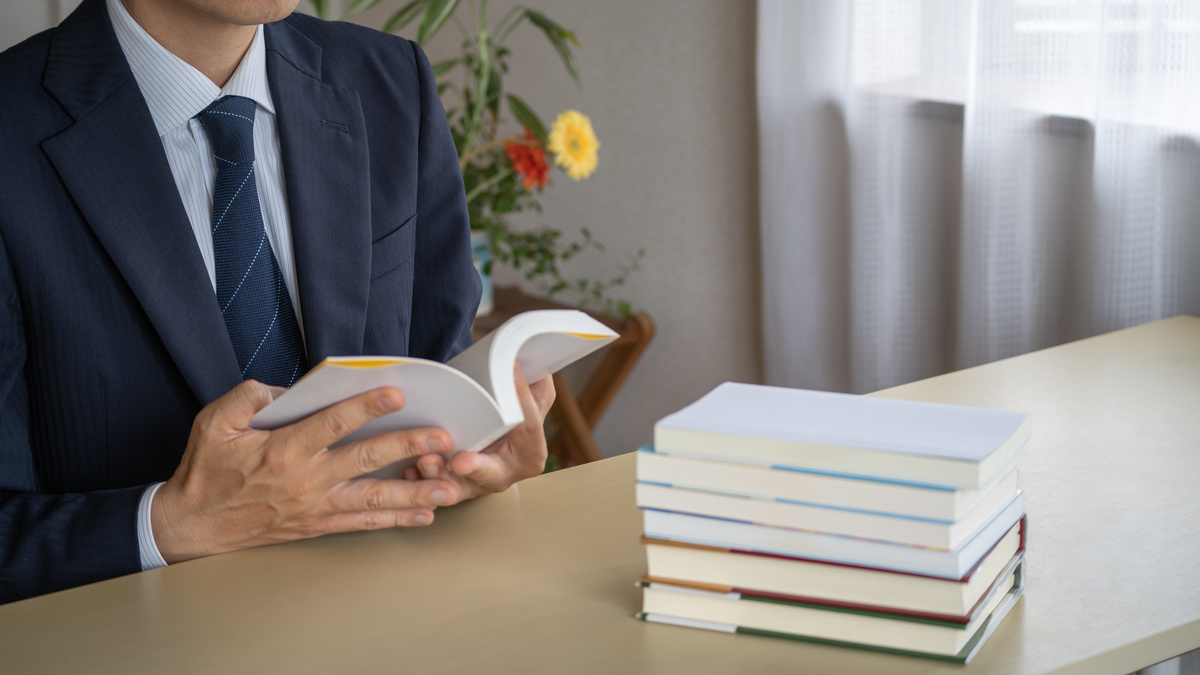
業種によって休日が異なるためです。
業種ごとの効果的な曜日は、以下の通りです。
| 業種 | 効果的な曜日 |
| 個人 | 土曜日、日曜日 |
| 一般企業 | 火~木曜日 |
| 不動産業 | 木~火曜日 |
| 美容室・理容室 | 火~日曜日 |
個人に営業電話をする場合は、在宅している可能性が高い週末に電話をかけるとよいでしょう。
一般企業は火曜日から木曜日が営業電話やテレアポに効果的です。
ただし、週の始まりである月曜日は定例の会議が入っている可能性が高く、電話がつながりにくいでしょう。
また、金曜日は仕事の締め切りが設定されていることが多く、担当者が忙しくて電話に出られないことも考えられます。
さらに、業種ごとの休日を避けて営業電話することも重要です。
美容室・理容室は月曜日が休み、不動産業は火曜日や水曜日が休みであることが一般的です。
マナー違反になる時間帯について

電話をかける際に注意すべき時間帯があります。
その時間帯に電話をすると、 顧客にマナー違反だと感じさせて信頼を失う恐れもあります 。
マナー違反になる時間帯を理解し、顧客の印象を悪くしないようにしましょう。
ランチタイム
ランチタイムに電話をかけることは、マナー違反であるとされています 。顧客が休憩している時間帯であり、営業の電話を嫌うためです。
一般的なランチタイムである12〜13時の時間帯は、連絡を避けましょう。
忙しい時間帯や繁忙期を避ける
顧客の忙しい時間帯や繁忙期は避けましょう 。忙しいときに電話がかかってきて、好印象を抱く顧客は少ないでしょう。
個人法人を問わず、1日のうちで忙しい時間帯は、連絡を避けるのがベターです。
忙しい時間帯は、個人と法人で異なります。
例えば、主婦が忙しい時間帯は、昼食や夕食などの家事をしている時間帯です。
法人の場合は、朝礼などがある始業直後や打合せが始まることの多い13時頃が忙しい時間帯とされています。
また、一般的に3月は期末であるため、繁忙期である企業が多いです。
ただし、繁忙期は業種により異なるため事前に調べるとよいでしょう。
始業・終業のタイミングに注意する
朝の9~10時など、始業からすぐの時間は、当日の予定確認や朝の打ち合わせ、メールの確認・返信など、1日の中でも慌ただしい時間帯です。
また、終業間際の17~19時の時間帯は、日報の作成や片付けなどに集中している可能性が高いです。
これらの時間は、 電話をしても出てもらえない可能性が高いほか、電話に出ても営業やテレアポだと気づかれるとすぐに電話を切られてしまう可能性が高くなります 。
「忙しい時間にも関わらず電話をかけてきた」ということで心象が悪くなる可能性もあるため、始業後・終業前の1時間程度は、電話をかけないようにしましょう。
営業電話・テレアポが違法になる時間帯はあるのか?

ランチタイムや忙しい時間帯を避けることは営業電話のマナーとして大切ですが、電話をかけると違法になる時間帯はあるのでしょうか。
結論としては、 電話営業が禁止されている時間帯は法律で定められています 。
違法行為とみなされると業務改善命令や業務停止命令を受ける可能性もあるため、注意が必要です。
本章では、営業電話や営業電話に適用される法律を紹介し、営業電話が違法となる時間帯やそのほかの違法行為について解説します。
テレアポや営業電話に適用される法律
営業電話・テレアポに適用される法律は、特定商取引法です。
特定商取引法は事業者による勧誘行為に関するルールを定めたものであり、以下のような事業に適用されます。
- 電話勧誘販売
- 訪問販売
- 通信販売
特定商取引法の目的は、強引な勧誘行為を防止して消費者の利益を守ることです。
特に営業電話は手軽に始められる勧誘行為ですが、 特定商取引法の内容を理解した上で運用する必要があります 。
営業電話・テレアポが違法となる時間帯
特定商取引法では「迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること」が禁止行為として定められています。
条文では具体的な時間帯は定められていません。
ただし、令和4年に出された法律の運用に関する通達「特定商取引に関する法律等の施行について」では、迷惑を覚えさせるような仕方に関して以下のように言及しています。
「具体的には、正当な理由なく不適当な時間帯に(例えば午後9時から午前8時まで等)勧誘をすること、長時間にわたり勧誘をすること、執ように何度も勧誘をすること等(*1)」
つまり、 21時から翌朝8時までの電話は法律的に不適切であるということです 。
アポイントが取れている場合を除き、21時から翌朝8時までの電話は控えましょう。
(*1)引用「特定商取引に関する法律等の施行について」
営業電話・テレアポに関するそのほかの違法行為
正しく営業電話を行うためには、特定商取引法で定められている禁止事項を理解することが大切です。
特に 気を付けるべき違法行為は、以下の6つです 。
- 事業者名を名乗らずに勧誘する
- 勧誘目的の電話であることを隠す
- 断られた相手に再度電話をかけて勧誘する
- 故意に事実とは異なる説明をする
- 威圧的・高圧的な態度で契約を迫る
- 契約後に書面を交付しない
最低限のルールを守って、正しく営業電話を行いましょう。
営業電話・テレアポの違法行為に関しては、「電話営業は違法?電話をかける際の注意点を解説」でも詳しく解説しています。
営業電話・テレアポが上手くいかないときの対処方法

営業電話が上手くいかないとき、時間帯以外で以下のようなポイントを意識すると記載する
- 繋がらないのが普通と考える
- 断らせない会話術を意識する
- 自分の都合を押し付けない
- トークスクリプトの内容を精査する
- 1日に複数回かけてみる
- いつであればつながりやすいか質問する
- フォローと営業電話は時間を分ける
- 電話以外の方法も検討する
以下の対処方法をとることで、電話がつながる確率を上げられます。
繋がらないのが普通と考える
営業電話やテレアポでは、 「断られて当たり前」という前提で取り組むことが大切 です。
電話を受ける側にとっては突然の連絡であり、こちらのサービスや商品に対して興味やニーズを持っていない可能性もあります。
つまり、 「電話に出てもらえない」「早い段階で断られる」は通常の反応 であり、それ自体が失敗ではありません。
必要以上に落ち込まず、反応の良かったポイントや断られた理由を分析して、次の架電に活かしましょう。
電話に出やすい曜日や時間帯など、次につながる情報を聞き出すことができれば十分です。
用件に端的に伝える
忙しい中で電話を受けてくれる相手にとって、話が長くて要点が見えない営業電話は大きなストレスになります。
「○○株式会社の△△と申します。御社の〇〇部門に向けて業務効率化のご提案でご連絡しました。」など、まずは 自社名と要件を簡潔に伝え、相手のストレスを軽減する意識を持ちましょう。
「誰が・何の用件で・何の目的で」電話をしているのかをできるだけ短く伝えることを意識してみてください。
声のトーンや速さに問題がないか確認する
営業電話・テレアポでは相手の顔が見えないため、声が唯一の情報伝達手段になります。
どんなに良い内容でも、早口だったり、声が小さくこもっていたりすると、相手には伝わりません。
少しでも印象を良くして、話を聞いてもらいやすくするために、 「ややゆっくりのペースで話す」「明るくはっきりした声のトーンを意識する」「語尾を丁寧にはっきりと発音する」 などのポイントを意識しましょう。
自分の声のトーンやスピードがどのように伝わっているのかを把握するために、録音して自分の話し方を客観的にチェックするのも有効です。
自分の都合を押し付けない
営業電話は、基本的に相手の業務時間に割り込むような形で行われます。
そのため、 自分の都合を一方的に押し付けるのではなく、相手の時間を尊重する姿勢が非常に重要 です。
「お忙しいところ恐れ入ります。お時間を改めた方がよろしいでしょうか?」など、 相手を気遣う一文を端的に含ませ、対応しやすい曜日や時間を確認して次回につなげるのがベスト です。
無理に話を続けようとしたり食い下がったりすると印象が悪くなり、電話に出てもらえなくなる可能性が高いので注意してください。
トークスクリプトの内容を精査する
「電話に出てもすぐに切られてしまう」「担当者に取り次いでもらえない」というケースが続く場合は、トークスクリプトの挨拶やフロントトークに問題がある可能性が高いです。
このようなときは、 録音内容などを元に、特に「最初の30秒~1分」に注目して原因を分析 しましょう。
「挨拶が長すぎないか」「要件が分かりにくくないか」「相手にメリットが伝わっているか」などのポイントをチェックし、トークスクリプトの内容を精査・改善しましょう。
「挨拶を最小限に抑え、フロントトークの商品紹介で数字や事例を簡潔に含ませる」など、具体的な成果や関心の高い話題を導入に入れることで、会話がスムーズに進みやすくなる ので試してみてください。なお、トークスクリプトの作り方や例文は以下の記事でもくわしく紹介しています。興味がある方は合わせてご確認ください。
関連記事: 電話営業トークスクリプトの例文・作り方は?アポ率2.6倍!買いたくなるキラートーク例
1日に複数回かけてみる
電話をかけてつながらない場合は、 同じ日に何度か電話をかけてみるとよいでしょう 。
なぜなら、担当者が電話に出られる時間帯は複数あるためです。
トイレや会議などで離席していて電話に出られない場合も考えられます。
一度で諦めず、同じ日に時間帯をずらして電話をかけるようにしましょう。
いつであればつながりやすいか質問する
担当者が不在であっても、すぐに電話を切ってはいけません。
電話の相手に、 担当者がつながりやすい時間帯を質問することがポイントです 。
教えてもらった時間にかけ直せば、担当者と話せる可能性があります。
もし担当者の名前がわからない場合は、電話の相手に尋ねるべきです。
フォローと営業電話は時間を分ける
フォロー電話は、HPからの資料請求や問い合わせなど、顧客側からのアクションがあった場合にかける電話のことです。また、商談中の顧客への連絡もフォローに含まれます。
どちらを優先すべきかわからないという方もいるかもしれませんが、 緊急度が高い場合を除いて、適切な時間帯は「営業電話」をメインに行い、余った時間でフォローを行うのがおすすめ です。
営業電話はどうしても体力や気力を消耗しやすい傾向があるほか、難易度も高いため「良い時間帯」は、できるだけ新規の営業電話で有効活用しましょう。
電話以外の方法を検討する
「営業電話の成果がなかなか上がらない……」という方は、その他のアプローチも検討しましょう。
目的はアポイントや商談を獲得することで、電話以外の手段の方が効果が出るケースもあります。電話以外の顧客へのアプローチとして代表的なのは以下です。
【代表的な顧客へのアプローチ】
・ダイレクトメール
・SNS
・LINE公式アカウント
・Webセミナー・動画コンテンツ
など
ターゲットによっては、このようなアプローチが向いているケースもあります。 限られたリソースを最適に使うためにも、「相手に合わせた手段」を意識することが大切 です。
無理に電話にこだわるのではなく、複数のアプローチを柔軟に試し、施策全体での成果向上を目指しましょう。
営業電話はつながりやすい時間帯や曜日を考慮して実施しよう
営業電話が効果的な時間帯は、法人と個人で異なります。
21時から翌朝8時の間に営業電話をすることは法律で禁じられているため、注意が必要です。
さらに時間帯だけでなく、 業種により電話がつながりやすい曜日もあるので、営業電話をする際の参考にしてください 。
営業電話など営業活動に役立つツールを探している方には、2,600社(2025年7月時点)に導入された実績のあるリスナビがおすすめです。
効率的に架電できるようになるだけでなく、架電の結果やデータを分析して電話営業の効率を高められます。
営業電話を実施している企業は、ぜひリスナビの導入を検討してください。
|
■アウトバウンド特化のコールシステム lisnavi(リスナビ) lisnavi(リスナビ)は、累計導入社数2,700社(2025年7月時点)を誇る、株式会社Scene Liveが販売するCTIシステムです。
などなど、電話業務の課題解決に優れています。 さまざまな業務・現場の需要に対応する柔軟性・カスタマイズ性を兼ね備えたCTIシステムです。 柔軟性や効率性に優れたアウトバウンド向けCTIをお探しの方は、ぜひこちらから詳細をご確認ください。 |

-
Written by株式会社Scene Live マーケティング部
コラム・セミナー・お役立ち資料を通して、電話業務や営業活動を効率化させる実践的な情報を配信しています。ツールの使い方や業界の動向など、最新情報を発信し続けることで電話業務に携わるすべての人にとって信頼できる情報源になることを目指しています。
COLUMN合わせて読まれているコラム